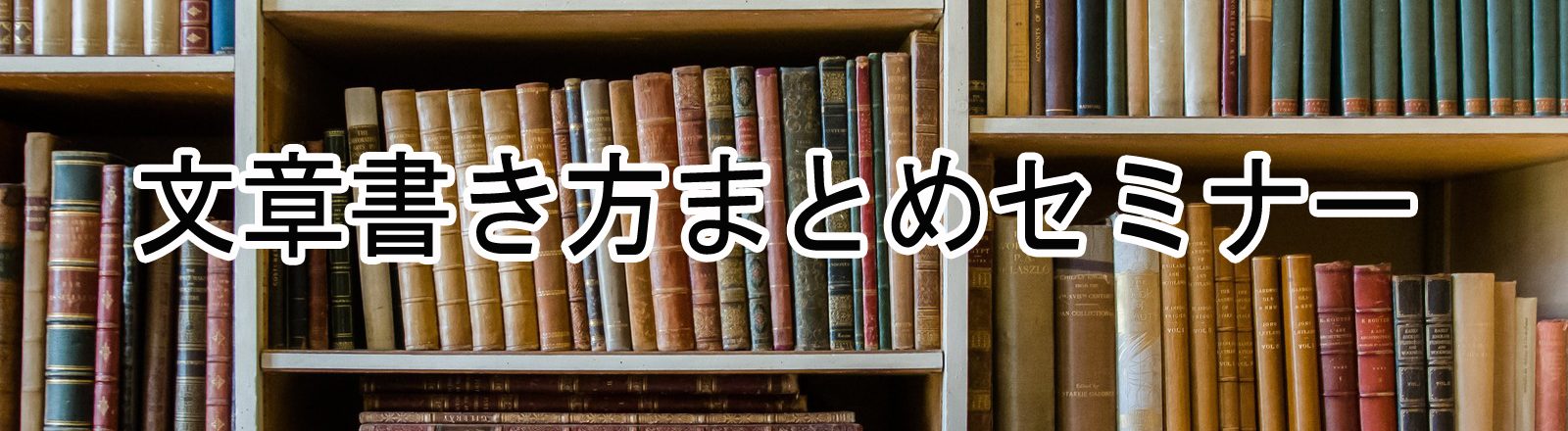『私は、〇〇をした』……これは、文章の基本構成ですね。
正しく書かれた文章なので、間違ってはいません。
しかし、『私』のような自分を表現する言葉が散りばめられた文章は、読みづらくなってしまいます。
何故、一人称である『私』を入れた文章が読みづらくなるのか、解説していきます。
一人称の役割
一人称とは、人称が一人と意味です。つまり、話し手を表しています。
『私は歌いました』なら、これは話し手が歌っていることを意味しているわけです。
何故、一人称が必要なのかというと、登場人物が複数いるとき、誰が喋っているのかが分かるようになるからです。
例
逃げるしかなかった。でも捕まってしまい、もうダメだと諦めた。しかし、その腕を振り払い、田中くんは逃げることができた。
この例文は、一人称が抜けているばかりに、誰が逃げているのかが分からなくなっている文章です。
『でも捕まってしまい、もうダメだと諦めた』と書かれていたら、普通は『私』だと思ってしまいます。
しかし、『田中くんは逃げることができた』と最後に書かれているため、これは『私』が『田中くん』を見ており、心中で「もうダメだ」と思っている内容だったのです。
たった一つの一人称を加えるだけで、この難解な文章は読みやすくなります。
例
田中くんは逃げるしかなかった。でも捕まってしまい、私はもうダメだと諦めた。しかし、その腕を振り払い、彼は逃げることができた。
こちらの文章のほうが読みやすいうえに、意味がしっかりと通じますね。
このように登場人物が複数いる場合、一人称がなければ誰のセリフなのかが見えてこないのです。
私(自分)を表現する一人称を少なくする
さきほどの例文を読むと、私(自分)を表現する一人称を使わなければならないと思ってしまいがちです。
しかし、過度な『私』は文章の流れを悪くするため、読みづらくなります。
例文
私は本当に怒っていた。私の大切な花瓶をあろうことか、私が何度も飼うのを反対していた猫が壊したからだ。あの猫は、私の忠告を聞かない妻と同じような顔をしながら、私の前を通り過ぎた。
これは、『私』という言葉が煩わしく思ってしまう文章ですね。
冒頭で『私は本当に怒っていた』と書かれているので、この文章は『私』の話であることは明白です。
にも関わらず、『私の大切な花瓶』『私が何度も飼うのを反対していた』と『私』を入れてしまっています。
ここに『私』が入っていなくても、意味は通じるはずです。なので、わざわざ自分の行動を表現する必要はないのです。
例文
私は本当に怒っていた。大切な花瓶をあろうことか、何度も飼うのを反対していた猫が壊したからだ。あの猫は、聞く耳を持たない妻と同じような顔をしながら、平然と前を通り過ぎた。
どうでしょうか。『私』がなくなった分、さきほどよりも読みやすくなっていると思います。
このように、不必要な『私』は文章の流れを悪くするのです。
例文
私が勤務するのは、白鳥商事です。日々の業務は、おもに外回りです。
私の仕事は、他にもあります。このシーズンは、新入社員の指導も行っています。
そのせいもあり、最近は定時に自宅へ帰ることができず、私は妻と喋る機会が少なくなってきました。
こちらの例文は、どうでしょうか。さきほどに比べて、とくに違和感がないように見えます。
その理由は、文章が改行されており、一行ごとに『私』が一つずつしかないからです。
ただし、この文章でも『私』を入れる必要はありません。
『私』を入れなくても、意味が通じるからです。
例文
私が勤務するのは、白鳥商事です。日々の業務は、おもに外回りです。
仕事は、他にもあります。このシーズンは、新入社員の指導も行っています。
そのせいもあり、最近は定時に自宅へ帰ることができず、妻と喋る機会が少なくなってきました。
二行目と三行目の『私』を抜いたことで、文章の内容に集中することができるようになりました。
このように、改行したあとでも『私』の話が続くのなら、わざわざ入れる必要はないのです。
まとめ
『私』は、文章の話し手を表現するために必要な一人称です。
文章の中に登場人物が複数いるときに利用することで、『自分』と『相手』を区別することができるようになります。
ただし、不必要な『私』は文章を読みづらくします。
文章を読み返し、『私』がなくても内容が通じる場合は削りましょう。
また、他にも『私』が不要なケースがあります。
それは『ビジネス文書』です。
『ビジネス文書』で『私』を表現する必要はないからです。