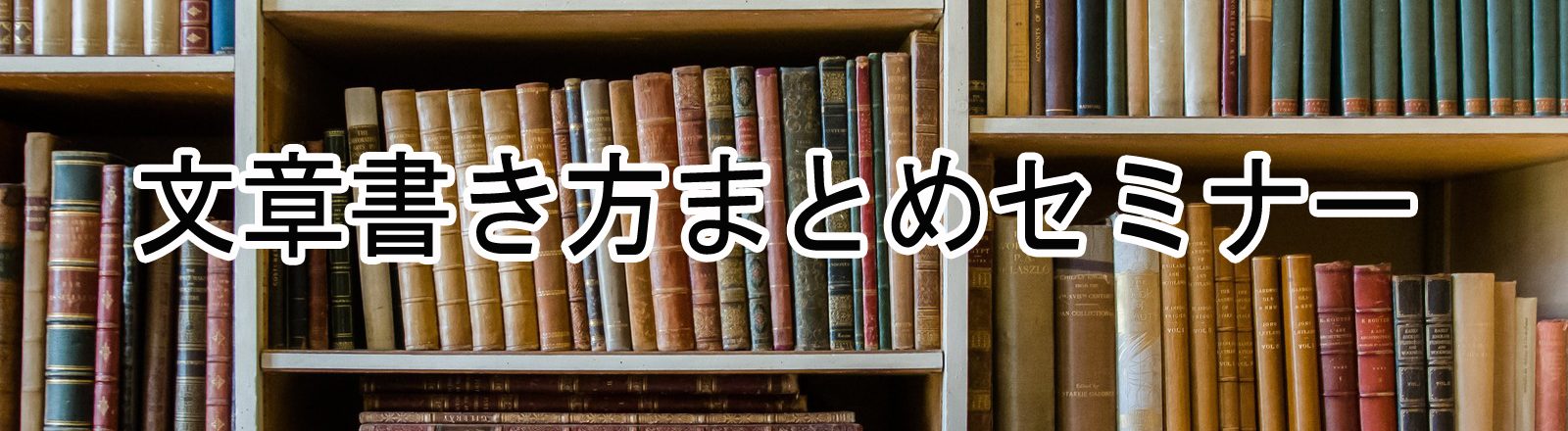読みやすい文章の書き方講座、第7回の記事になります。
第7回目は、文章の漢字の割合をどれぐらいにするかを解説します。
漢字が文章に与える影響
漢字を使用することで、文字の分量を減らすことができます。
それだけでなく、文章を見やすくする効果があります。
「わたしは、さんぽをすることがすきだ」
上記の例文のように、ひらがな表記だけで文を作ってしまうと、どこからが単語か接続詞か、一目では分かりづらいです。
「わたしは、散歩をすることが好きだ」
単語を漢字に直すだけで、文章の内容がスムーズに入ってくると思います。
適切な場所に漢字をもってくることで、最後まで読みやすい文章を書くことができるのです。
漢字の割合によって文章が窮屈に見える
このサブタイトル『漢字の割合によって文章が窮屈に見える』を見ていただくと、すでに分かると思います。
文章の中に漢字が多くなると、このように窮屈なイメージを読み手に与えます。
勉強が嫌いな相手に、辞書を見せるのと同じことです。
『漢字が文章を窮屈にみせる』と直すだけで、少しは余裕がある文章に見えます。
では、以下の例文ではどうでしょうか。
「私達は、耐えがたい苦痛を毎日強いられて来た」
暗い内容であるにも関わらず、漢字づくしで表現されてしまっては、こちらの気も滅入ってしまいます。
「私たちは、耐えがたい苦痛を毎日しいられてきた」
幾分かは、開放的な文章になったと思います。
文章は、一行で終わるものではありません。
長々と読まされたとき、この違いは確実に読みやすさに繋がります。
漢字は文章を読みやすくしますが、日本人が本当に読みやすいのは『ひらがな表記』です。
文章を構築するとき、ひらがな表記を六~七割で意識して書いてみましょう。
なので、漢字の割合は三割ぐらいが適切でしょう。
まとめ
漢字を用いるとき、必ず考える問題があります。
それは、難しい漢字を使うべきかどうか、です。
『躊躇い』『著しい』『芳しい』などは耳にする言葉ですが、漢字にすると読めない方も多いようです。
読みやすい文章を追及するとき、確かに難しい漢字は避けるべきです。
しかし、文章とは相手に知識を与える教科書になり得ることを忘れてはいけません。
相手に教えるつもりで文章を書くことも、読み手を思って書いていることに通じます。
結果的に、読みやすい文章に繋がるのです。
目次
読みやすい文章の書き方講座 第1回『文末は「です」「ます」で統一する』
読みやすい文章の書き方講座 第2回『「ら」「い」抜きで書かない』
読みやすい文章の書き方講座 第3回『句点と読点の正しい打ち方』
読みやすい文章の書き方講座 第4回『5W1Hとは?順番や意味は?』
読みやすい文章の書き方講座 第5回『重複表現、二重表現がないかチェックする』
読みやすい文章の書き方講座 第6回『カタカナ表記にする言葉は外来語と効果音』
読みやすい文章の書き方講座 第7回『漢字は少なく「ひらがな」を主体にする』
読みやすい文章の書き方講座 第8回『段落の意味、つけ方を覚えて文章をまとめる』
読みやすい文章の書き方講座 第9回『名詞や動詞を際立たせて、形容詞、副詞をなくす』
読みやすい文章の書き方講座 最終回『推敲を繰り返すだけで文章は良くなる』